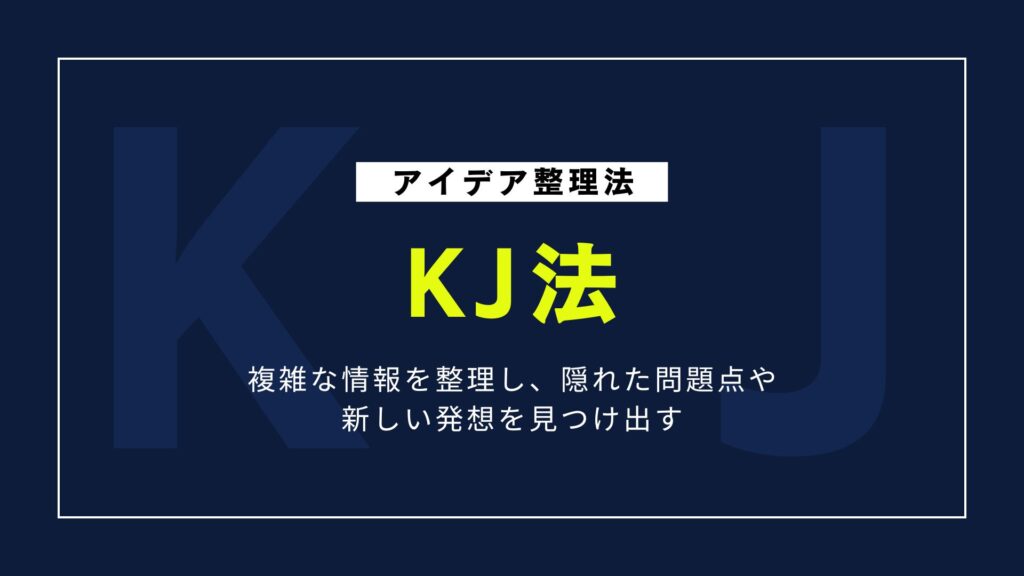
複雑な情報を整理し、隠れた問題点や新しい発想を見つけ出す強力な手法が「KJ法(ケイジェイほう)」です。
この記事では、KJ法を初めて使う初心者の方でも安心して実践できるよう、その基本的なやり方を4つのステップに分けて、誰でも簡単にできる形で徹底解説します。
目次
KJ法とは?目的と特徴を初心者向けに整理
KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎(かわきた じろう)氏が考案した、断片的な情報やアイデアを効率的に整理・分析するための手法です。「KJ」という名前は、考案者のイニシャル(Kawakita Jiro)に由来しています。
この手法の最大の目的は、一見するとバラバラに見える多数の情報を、カード(付箋など)を使ってグループ化し、それらの関係性を図解することで、情報の「全体像」や「構造」を視覚的に明らかにすることです。
頭の中だけでは処理しきれない複雑な問題を、手を動かしながら整理することで、思考がクリアになり、本質的な課題の発見や、創造的なアイデアの創出(統合)につながります。
KJ法が必要とされる理由(会議・企画・調査で役立つ場面)
KJ法は、特に以下のような「情報が混沌としている」場面で真価を発揮します。
- 会議やワークショップの後:「たくさんの意見が出たが、議論が発散したままで結論が出ない」「誰が何を言ったか、重要なポイントが何だったかを見失ってしまった」→KJ法で意見を整理すれば、参加者の共通認識(コンセンサス)を形成しやすくなります。
- 新企画の立案・アイデア出し:「新商品のアイデアが断片的にしか出てこない」「集めた市場データや競合情報をどう企画に活かせばいいか分からない」→KJ法で関連する情報をグループ化することで、アイデア同士が結びつき、新しい企画の切り口が見つかります。
- 調査やインタビューの分析(UXリサーチなど):「ユーザーインタビューで多くの発言(事実)を集めたが、本質的なニーズ(インサイト)が見えない」「アンケート結果をどう解釈し、次のアクションにつなげるべきか悩んでいる」→KJ法は、顧客の生の声(定性データ)を整理し、隠れた課題や要望を体系的に把握するための強力な分析ツールとなります。
KJ法とブレストとの違い(発想法ではなく“整理法”である点)
初心者がよく混同しがちなのが「ブレインストーミング(ブレスト)」と「KJ法」の違いです。この二つは目的が全く異なります。
- ブレスト(発想法)
目的は「アイデアの“量”を出すこと」です。質より量を重視し、批判をせずに自由な発想で意見を拡散させます。 - KJ法(整理法・統合法)
目的は「出されたアイデアを“整理・統合”すること」です。拡散した情報をグループ化し、構造化することで、一つの方向性や結論へと収束させます。
つまり、「ブレスト」でアイデアをたくさん出した“後”に、「KJ法」でそれをまとめる、というのが一般的なやり方です。KJ法は、発想を生み出すだけでなく、その発想を論理的に組み立て直すための手法なのです。
KJ法の基本ステップ|初心者でもできる4つの流れ
KJ法のやり方は、大きく分けて4つのステップで構成されています。この流れさえ押さえれば、初心者でも簡単に実践できます。
ここでは、最も基本的な紙(付箋)を使ったやり方を紹介します。
ステップ1:紙にアイデアを書き出す「カード作成」

まずは、整理したい情報やアイデアを、1枚ずつ小さなカード(付箋や情報カード)に書き出していきます。
- 準備するもの:
- 付箋(ポストイットなど。貼り直しが簡単なため推奨)
- ペン(太めのサインペンなど、見やすいもの)
- 情報を貼る広いスペース(大きな模造紙、ホワイトボード、壁、広い机など)
- ルールのポイント:
- 「1カード=1アイデア」の原則を徹底します。「AとB」のように2つの情報が入りそうな場合は、必ず2枚のカードに分けて書きます。
- 文章は短く、簡潔に(体言止めや「〜である」など)。誰が見ても意味が分かる言葉で書きます。
- ブレストなどで出た意見を書き出す場合は、参加者の発言をそのまま(解釈を加えず)書き写すのがコツです。
- 思いつく限り、数十枚〜百枚以上書き出します。
ステップ2:似ているカードをまとめる「グルーピング」

すべてのカードを書き出したら、それらを広いスペースにランダムに広げます。ここからがKJ法の本番です。
- やり方:
- まず、全体を眺めながら、「なんとなく似ている」「関連性があるな」と感じるカード同士を近くに寄せていきます。
- 2〜5枚程度の小さなグループ(島)をたくさん作っていきます。
- コツと注意点:
- 直感を信じる
このステップでは、論理的に「分類」しようとしないでください。「Aカテゴリ」「Bカテゴリ」のように、あらかじめ分類軸を決めてはいけません。あくまで「なんとなく近い感じがする」という主観的な感覚を大切にします。 - 無理にまとめない
どのグループにも属さないと感じるカード(「一匹狼」と呼ばれます)は、無理にどこかに入れず、一枚のまま放置しておきます。それが重要なヒントになることもあります。 - 全員で動かす
グループワークで行う場合は、参加者全員が立ち上がり、無言でカードを動かしながら、納得のいく配置を探ります。
- 直感を信じる
ステップ3:グループに名前をつける「ラベル付け」
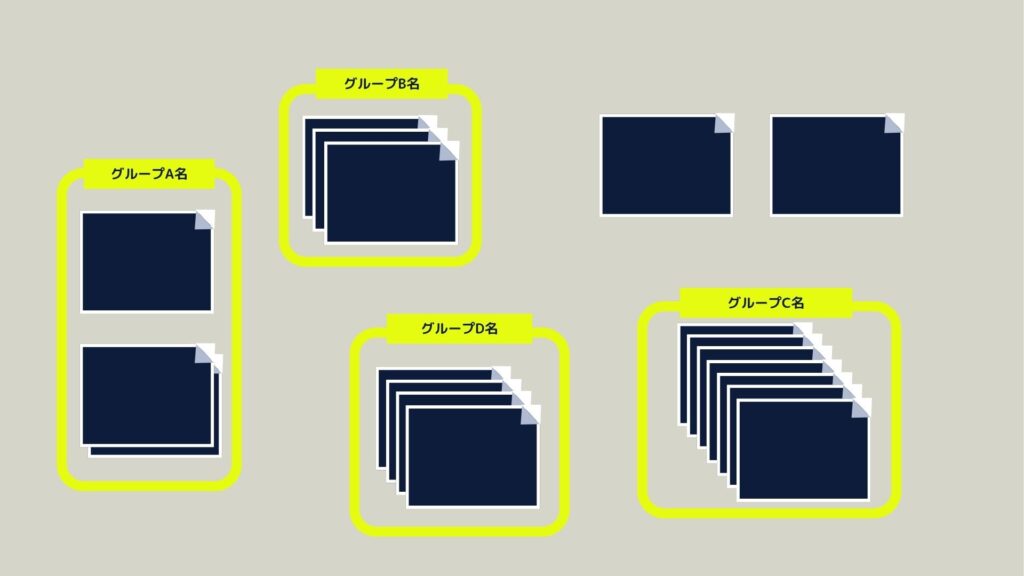
小さなグループができたら、次はそのグループに「見出し」をつける作業(ラベル付け)を行います。
- やり方:
- 作ったグループのカード(2〜5枚程度)を眺め、「これらのカードが共通して言いたいことは何か?」考えます。
- そのグループの内容を的確に要約する「見出し(ラベル)」を考え、新しいカード(色を変えると分かりやすい)に書き込み、そのグループの近くに置きます。
- コツと注意点:
- 元のカードの言葉を使わない: グループ内のカードの言葉をそのまま使うのではなく、それらを「抽象化」「要約」した新しい言葉で表現するのが重要です。
- (例)「A社の機能がすごい」「B社のデザインが良い」「C社は安い」というカードのグループ
- 悪い例:「競合の状況」(元の言葉を使いすぎ)
- 良い例:「競合各社が独自性で勝負している」
- このラベル付けの作業を通じて、断片的な情報が意味のある「かたまり」として認識できるようになります。
ステップ4:つながりを並べる「図解化」

最後に、ラベル付けされたグループ同士の関係性を読み解き、全体像を明らかにします。
- やり方:
- まず、ステップ3で作った「ラベル付きのグループ」同士を、さらに似ているもので集めて「中グループ」「大グループ」を作っていきます。(この時も、新しいラベルを付けます)
- 最終的に出来上がったいくつかの大きなグループを、模造紙やホワイトボードの上で配置し直します。
- グループ同士の関係性(例:Aが原因でBが起きる、CとDは対立している、EはFに含まれる、など)を考え、線や矢印(→)、囲み線などでつなぎ、関係性を図解します。
- 完成:
これにより、バラバラだった情報が、論理的なつながりを持った「構造図」として可視化されます。「ああ、この問題の根本原因はここにあったのか」「次に私たちが取り組むべき優先順位はこれだ」といった、深い洞察が得られるようになります。
KJ法を簡単に進めるための実践テクニック
基本的なステップは上記の通りですが、より簡単に、より効率的に進めるためのテクニックをいくつか紹介します。
意見が出にくい時に使える補助質問リスト
ステップ1の「カード作成」で、アイデアや情報が十分に出てこない場合があります。特に一人でKJ法を行う(セルフKJ法)時に陥りがちです。
そんな時は、以下の「補助質問」を使って、思考を深掘りしてみてください。
| 質問のタイプ | 具体的な質問例 |
| Why?(なぜ?) | 「なぜ、そう感じたのか?」「なぜ、それが必要なのか?」 |
| So What?(だから何?) | 「その事実から、何が言えるのか?」「それが起きると、どうなるのか?」 |
| How?(どうやって?) | 「具体的には、どういうことか?」「どうすれば、それを実現できるか?」 |
| Who/When/Where?(5W1H) | 「それは、誰が・いつ・どこで感じたことか?」 |
グループワークで意見を引き出す進行のポイント
複数人(グループワーク)でKJ法を行う場合、進行役(ファシリテーター)の役割が重要です。
- 「カード作成」は静かに集中:アイデアを書き出す際は、おしゃべりをせず、各自が黙々と書き出す時間を確保します(例:10分間)。これにより、他の人の意見に引っ張られない多様な意見が出やすくなります。
- 「グルーピング」は対話を促す:カードを動かす際、「なぜ、あなたはこの2枚を一緒にしたのですか?」と理由を尋ね、メンバー間の認識をすり合わせます。
- 「ラベル付け」で納得感を醸成:グループの「見出し」を考える作業は、最も議論が白熱する部分です。「このグループはAという名前が良い」「いや、Bという意味も含まれている」といった議論を通じて、チームの理解が深まります。
- 否定しない雰囲気づくり:KJ法は「まとめる」作業ですが、その過程で出る意見を否定してはいけません。進行役は「面白い視点ですね」「そういう考え方もありますね」と、あらゆる意見を受け入れる雰囲気を作ることが、簡単かつ効果的に進めるコツです。
KJ法が役立つ具体的な活用シーン
KJ法は、ビジネスから学業まで、非常に幅広く応用できる思考整理術です。
企画立案でのアイデア整理の具体例
「新しいECサイトの集客施策」についてブレストを行ったとします。
「SEO対策」「SNS広告」「インフルエンサー活用」「ポイント還元」「限定セール」「UI改善」…など、50個のアイデアが出ました。
これらをKJ法で整理します。
- カード作成
50個のアイデアを50枚の付箋に書き出す。 - グルーピング
「SEO」と「広告」は近いな、「ポイント」と「セール」も近いな、とグループを作る。 - ラベル付け
「SEO/広告」グループに【新規顧客の獲得】、「ポイント/セール」グループに【既存顧客の購買促進】、「UI改善」グループに【サイト内回遊率アップ】といったラベルを付ける。 - 図解化
【新規顧客の獲得】→【サイト内回遊率アップ】→【既存顧客の購買促進】という流れ(因果関係)が見えてくる。
→結果:
「まずはサイトのUI改善(回遊率アップ)をしないと、集客(新規獲得)しても効果が薄い。優先順位はUI改善だ」という戦略的な意思決定が可能になります。
UXリサーチやインタビュー内容のまとめに使う方法
アプリ開発のために、5人のユーザーにインタビューを行ったとします。膨大な量の発言録(ログ)が集まります。
- カード作成
インタビューログから、ユーザーの「事実(〇〇を使った)」「感情(嬉しかった、イライラした)」「要望(〇〇が欲しい)」を抜き出し、すべてカード化します。 - グルーピング
複数のユーザーが共通して言及している「イライラした」体験や、「〇〇が欲しい」という要望をグループ化します。 - ラベル付け
(例)「ログイン画面が分かりにくい」「パスワード再発行が面倒」というカード群に、【認証プロセスのストレス】というラベルを付けます。 - 図解化
【認証プロセスのストレス】が【アプリの利用離脱】という結果につながっている、といった構造を明らかにします。
→ 結果:
感覚的だった「使いにくい」という感想が、「認証プロセス」という具体的な改善ポイントとして特定でき、開発の優先順位が決まります。
まとめ|KJ法を簡単に実践するために必要なポイント
最後に、この記事で解説した「KJ法」の簡単なやり方について、最も重要なポイントをまとめます。
「KJ法 簡単 やり方」で押さえるべき最重要ポイント
- KJ法は「整理法」
アイデアを「出す」ブレストとは異なり、出た情報を「まとめる・構造化する」ための手法です。 - 核心は「グルーピング」
情報を論理で「分類」するのではなく、直感で「似ているもの」を集める作業が最も重要です。 - 「ラベル付け」で抽象化
グループに名前を付ける作業を通じて、個別の情報が持つ「意味」を発見します。 - 「図解化」で全体像を把握
最終的に情報の関係性(構造)を可視化することで、本質的な課題や解決策が見えてきます。
初心者が今日から実践できるシンプルな手順の要点
KJ法は、決して難しい専門技術ではありません。初心者でも、以下の点を意識すれば今日から実践できます。
- まずは「付箋」と「ペン」、そして「広い場所」を用意しましょう。
- 「1カード=1アイデア」の原則だけは、必ず守ってください。
- ステップ2の「グルーピング」では、難しく考えすぎず、「なんとなく」の直感を信じて手を動かしてみてください。
- いきなり仕事の難しい課題で試す前に、まずは「今週末にやりたいこと」「冷蔵庫の中身でできる料理」といった身近なテーマで練習してみるのが、簡単に習得する近道です。
情報が溢れ、物事が複雑になりがちな現代において、混沌とした情報を整理し、本質を見抜く「KJ法」は、あらゆるビジネスパーソンや学生にとって強力な武器となります。会議や調査、企画で行き詰まった時は、ぜひこの簡単なやり方を試してみてください。
