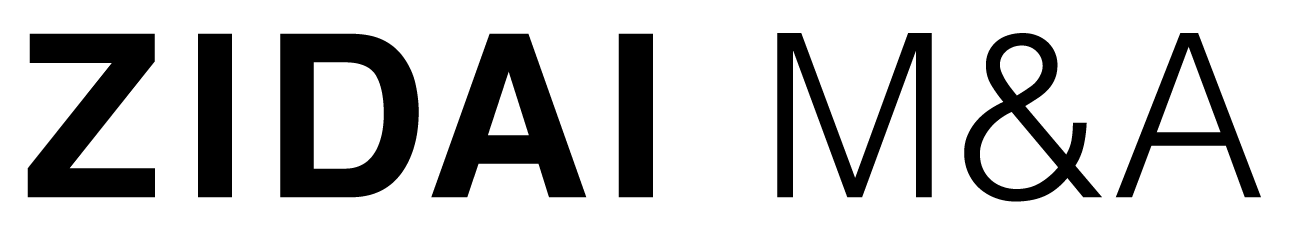バリュエーションとは、簡単に言えば「企業の価値評価(値付け)」のことです。
この記事では、M&Aや投資の基本となるバリュエーションの考え方、代表的な手法、そして活用シーンについて、初心者にもわかりやすく解説します。
バリュエーションとは何か
まずは、「バリュエーションとは」何か、その基本的な意味と役割から見ていきましょう。
バリュエーションの意味と役割
バリュエーション (Valuation) とは、直訳すると「価値評価」です。ビジネスの世界、特にM&Aや金融の分野では、「企業の価値(価格)を算定するプロセス」全体を指します。
例えば、あなたが家を買おうとするとき、その家の立地、築年数、広さ、周辺の相場などを調べて「この家は3,000万円くらいが妥当だろう」と考えるはずです。バリュエーションは、これと同じ作業を「企業」に対して行うことです。
上場している大企業であれば、株価(時価総額)という市場の評価がありますが、世の中の大半を占める未上場の会社には、公な株価はありません。そこで、その会社が持つ資産、将来稼ぐ力、市場での立ち位置などを分析し、「この会社の値段はいくらが妥当か」を専門的な手法で計算する必要があります。
バリュエーションの最大の役割は、企業価値を客観的な「物差し」で測り、交渉の「共通言語」を提供することです。売り手と買い手が「感覚」だけで「高い」「安い」と言い合っていても、交渉はまとまりません。客観的な計算に基づいた評価額があることで、初めて建設的な議論が可能になります。
M&Aや投資でバリュエーションが重要になる理由
バリュエーションは、主に以下の3つの場面で非常に重要になります。
- M&A(企業の買収・合併・売却)M&Aにおいて、バリュエーションは「取引価格」を決めるための根幹です。
- 買い手(買収側): 「いくらで買うか」を決めなければなりません。高すぎると投資資金を回収できず(高値掴み)、逆に安すぎると交渉が成立しません。適切な買収価格を見極めるために、バリュエーションは不可欠です。
- 売り手(売却側): 「いくらで売るか」を決める基準です。自社の価値を正当に評価してもらい、適正な価格(できるだけ高く)で売却するために、客観的なバリュエーションが交渉の拠り所となります。
- 資金調達(投資)スタートアップ(ベンチャー企業)が投資家から出資を受ける際にも、バリュエーションが使われます。
- 投資家は、「この会社は将来大きく成長しそうだ」と判断すれば、その「期待値」を含めたバリュエーション(評価額)で株式を取得します。
- 例えば、「バリュエーション10億円で1億円を調達」した場合、投資家は1億円を支払って、その会社の株式の10%(1億円 ÷ 10億円)を取得したことになります。
- 自社の経営状態の把握M&Aや投資の予定がなくても、自社の経営者が「今、自分の会社はいくらの価値があるのか」を把握することは重要です。事業承継で後継者に株を譲る場合や、単に経営の健全性を測る指標としても役立ちます。
企業価値を測る際に確認する基本的な視点
「バリュエーションとは、つまり会社の値段を決めること」と説明しましたが、その「値段」は一つの視点だけでは決まりません。企業の価値は、主に以下の3つの異なる視点から総合的に評価されます。
- 将来、どれだけ稼げるか?(収益性)
その会社が将来にわたってどれだけの利益やキャッシュフローを生み出す能力があるか、という視点です。M&Aの買い手にとっては最も重要な視点の一つです。 - 今、どれだけの資産を持っているか?(資産性)
その会社が「今すぐ解散したとして」、どれだけの資産(現金、不動産、機械、在庫など)が残り、負債(借金など)を差し引いていくらの純資産があるか、という視点です。 - 似たような会社はいくらで取引されているか?(市場性)
業種や規模が似ている上場会社が、市場(株式市場)でどれくらいの株価で評価されているか、または過去のM&Aでいくらで取引されたか、という相場(市場)を参考にする視点です。
重要なのは、バリュエーションに「唯一絶対の正解」はないということです。どの視点を重視するか、どの計算方法を選ぶかで結果は変わります。だからこそ、複数の手法を組み合わせて多角的に分析することが求められます。
代表的なバリュエーション手法の種類
企業の価値を評価する3つの視点(収益性・資産性・市場性)に基づき、バリュエーションの手法も大きく3つの「アプローチ」に分類されます。
時価総額で見る「マーケットアプローチ」
これは「市場性」の視点に立った評価方法です。似たような会社(上場企業)の株価や、過去のM&A事例(取引価格)を「市場の相場」として参考にします。
類似会社比較法(マルチプル法)
マーケットアプローチで最もよく使われる手法が「マルチプル法」です。マルチプルとは「倍率」という意味です。
▼計算のイメージ
- 評価したい会社(未上場)と業種や規模が似ている上場会社をいくつか選びます。
- その上場会社が、市場で「ある指標」の何倍の価値(時価総額)がついているか(=マルチプル)を計算します。
よく使われる指標:「EBITDA(イービットディーエー)」(税金や減価償却費を引く前の大まかな利益)や「純利益」など。 - 例えば、似た上場会社が平均して「EBITDAの8倍」の時価総額で評価されているとします。
- 評価したい会社のEBITDAが「1億円」だった場合、1億円 × 8倍 = 8億円 が企業価値の目安、というように計算します。
客観的な市場の相場を反映できるメリットがありますが、比較対象として適切な上場会社が見つからないと使えないデメリットもあります。
類似取引比較法
過去に行われた、評価したい会社と似たM&Aの取引事例を収集し、その際の「取引価格」が「EBITDAの何倍だったか」などを参考にする方法です。
将来の利益を基に考える「インカムアプローチ(DCF法)」
これは「収益性」の視点に立った評価方法です。その会社が「将来にわたって生み出すと予測されるキャッシュフロー(現金)」を基に価値を計算します。未来の期待値を評価に組み込むため、特に成長企業やスタートアップの評価で重視されます。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)
インカムアプローチの代表格が「DCF法」です。日本語では「割引現在価値法」と呼ばれます。
▼考え方のステップ
- 事業計画を作る
まず、その会社が将来(通常5年〜10年)どれくらいのキャッシュフローを生み出すかを予測した「事業計画」を作成します。 - 「今」の価値に割り戻す(割引)
将来もらえる「100万円」は、今すぐもらえる「100万円」よりも価値が低い、という考え方(時間価値やリスク)があります。
そこで、「割引率」という金利のようなものを使って、将来のキャッシュフローをすべて「現在の価値」に換算(割り戻し)します。 - 合計する
現在価値に割り戻した将来のキャッシュフローをすべて合計したものが、その会社の「事業価値」である、と評価します。
DCF法は、企業の将来性や個別の事情を最も詳細に反映できる理論的な手法ですが、「将来の事業計画」や「割引率」の設定次第で結果が大きく変わるため、作成者の主観が入りやすいという難点もあります。
純資産の大きさで判断する「コストアプローチ」
これは「資産性」の視点に立った評価方法です。会社の「貸借対照表(B/S)」に注目し、「今持っている純資産(資産 - 負債)」を基に価値を計算します。
簿価純資産法
貸借対照表に記載されている「帳簿上の数字」をそのまま使って、「純資産」を計算する最もシンプルな方法です。
時価純資産法(修正純資産法)
帳簿上の価格(簿価)は、買った時の価格であることが多いため、現在の実態(時価)とズレていることがあります。
例えば、昔1,000万円で買った土地が、今3,000万円に値上がりしているかもしれません。
そこで、土地、建物、有価証券(株など)といった資産を「現在の時価」で評価し直してから、「時価ベースの純資産」を計算する方法です。
コストアプローチは、客観的で計算が容易ですが、その会社が持つ「ブランド力」や「技術力」、「将来稼ぐ力(収益性)」といった「目に見えない価値(のれん)」を評価に反映できないというデメリットがあります。
▼ 3つのアプローチのまとめ
| アプローチ | 主な手法 | 特徴(メリット) | 注意点(デメリット) |
| マーケットアプローチ | 類似会社比較法(マルチプル法) | 客観性が高い、計算が比較的容易 | 適切な比較対象が見つからない場合がある |
| インカムアプローチ | DCF法 | 事業の将来性を最も反映できる、理論的 | 計画の立て方次第で結果が大きく変わる(主観が入りやすい) |
| コストアプローチ | 時価純資産法 | 客観性が高い、清算価値の把握に適している | 将来の収益性を反映できない |
バリュエーションの計算例と活用シーン
バリュエーションの考え方が、実際の場面でどのように使われるのかを見てみましょう。
シンプルな例で見るDCF法の計算イメージ
DCF法は難解なため、非常にシンプルな例で「将来のお金を現在の価値に割り戻す」というイメージを掴んでみましょう。
【前提】
- 毎年必ず「100万円」の利益を生み出す「魔法の箱(=会社)」があるとします。
- 将来のお金はリスクがあるため、年率10%で価値が割り引かれる(割引率10%)と仮定します。
【計算】
- 1年後にもらえる100万円の「現在の価値」
- 100万円 ÷ (1 + 10%) = 約90.9万円
- 2年後にもらえる100万円の「現在の価値」
- 100万円 ÷ (1 + 10%) ÷ (1 + 10%) = 約82.6万円
- 3年後にもらえる100万円の「現在の価値」
- 100万円 ÷ (1 + 10%) ÷ (1 + 10%) ÷ (1 + 10%) = 約75.1万円
- ...(これが永遠に続くと仮定)
DCF法では、このように計算した「将来生み出す価値の現在価値」をすべて合計したものが、その「魔法の箱」の今の価値(バリュエーション)である、と考えます。
スタートアップと成熟企業で評価が変わる理由
同じバリュエーションでも、会社の状況によって重視されるポイントが全く異なります。
- 成熟企業(利益が安定している企業)
- すでに安定した利益や資産があるため、コストアプローチ(資産)やマーケットアプローチ(相場)が比較的使いやすいです。
- DCF法を使う場合も、将来の予測が立てやすいため、堅実な評価になりがちです。
- スタートアップ(赤字だが急成長中の企業)
- 創業間もないため資産はほとんどなく、赤字経営も珍しくありません。そのため、コストアプローチで評価すると価値はゼロかマイナスになってしまいます。
- 「バリュエーションとは」将来への期待値を測るもの、という側面が最も強く出ます。
- スタートアップのバリュエーションは、「将来どれだけ爆発的に成長するか」という事業計画(インカムアプローチ=DCF法)や、似たようなスタートアップがいくらで資金調達したか(マーケットアプローチ)を基に、**将来の「期待値」**を大きく織り込んで決定されます。
M&Aの買い手・売り手で変わる評価の視点
バリュエーションは客観的な物差しですが、計算の前提条件の置き方によって、M&Aの「買い手」と「売り手」の立場で評価額が変わるのが一般的です。
- 売り手の視点
- 自社の価値をできるだけ最大化したいと考えます。
- 将来の事業計画を楽観的に(売上が大きく伸びるように)作成したり、自社の資産価値(時価純資産法)を高く見積もったりする傾向があります。
- 買い手の視点
- できるだけ安く買いたい(投資を早く回収したい)と考えます。
- 将来の事業計画を保守的・悲観的に(リスクを厳しく)見たり、DCF法の割引率を高めに設定したりする傾向があります。
- 買い手特有の視点
「シナジー効果」買い手は、売り手にはない独自の視点を持っています。それが「シナジー(相乗効果)」です。- 例えば、買い手が持つ強力な販売網(販路)を使えば、売り手の製品が今より3倍売れるようになる、と予測したとします。
- この「3倍売れる」ことによって増える利益は、売り手が自社だけで経営していたら得られなかった価値です。
- 買い手は、この「シナジーによる追加価値」を見込んで、売り手が考える評価額よりも高い価格を提示することができます。
このように、バリュエーションはあくまで「交渉の出発点」であり、最終的な取引価格は、売り手と買い手の交渉やシナジーの有無によって決まります。
まとめ:バリュエーションとは企業価値を判断するための共通言語
最後に、この記事の要点をまとめます。
バリュエーションの基本理解が投資・M&A判断の土台になる
「バリュエーションとは」何か、その基本を理解することは、M&Aや投資といった重要な経営判断を行う上での土台となります。
バリュエーションは、企業の「値段」がどのようなロジックで決まるのかを知るためのプロセスです。感覚的な「高い・安い」の議論ではなく、客観的な根拠に基づいた「物差し(共通言語)」を持つことで、リスクを抑えた合理的な判断や、相手との対等な交渉が可能になります。
企業の成長性・利益性・資産のバランスを見て評価することが重要
バリュエーションには「この方法だけが正しい」という絶対解はありません。
- マーケットアプローチ(市場の相場)
- インカムアプローチ(将来の収益力)
- コストアプローチ(現在の資産価値)
これら3つのアプローチ(視点)には、それぞれメリットとデメリットがあります。大切なのは、どれか一つに偏るのではなく、それぞれの特徴を理解した上で、複数の手法を組み合わせて多角的に企業の価値を分析することです。